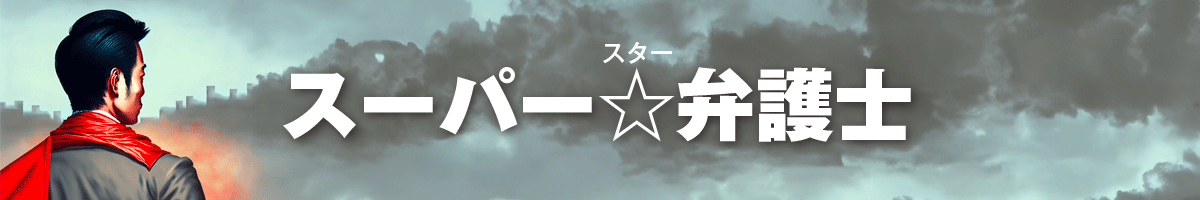
夕暮れの小学校に向かう。サッカー少年たちが芸術作品さながらの大きな壁に向かってボールを蹴っている。そこから少し離れて常に煙の立ち昇る無人焼却炉の近くに雲梯はまるで神からの試練かのように六本並べて地面とまっすぐに立てられていた。僕は長男に近所のおじさんがするようにパタゴニアの大自然を彷彿させるほどのほんのり甘い微糖の自然さで話し掛けた。
「ニュートン算はまだあの解き方で解いているのかい?」と僕は言った。「あの解き方はイマイチだな。お父さんの解き方でやった方がいいな。」
ニュートン算とは例えばお風呂の水を貯めているのに栓が抜けているみたいなどうしようもない状況でお風呂が満杯になる時間を算出する特殊算だ。そして、蛇口は必ずしも一つではなく、それぞれの蛇口から出てくる水は均等ではなかったりもする。僕は中学校受験をしていない。改めてこんな馬鹿げた問題があること自体が信じられない。そして、僕は長男が解くニュートン算の解き方が理解できなかった。
「もちろんあの解き方で解いているよ。正解が出ればいいってパパがいつも言うだろ。お勉強だからって。」と少し驚いた顔を示しながら長男は言った。
「つまりは、あれがお前のやり方なんだな?」
「それはママについて行ったボクへの非難を含ませた掛詞かい?」と長男は言った。図星だった。彼は続けた。「俺は俺のやり方でパパを超える。センター試験を受けるんだ。パパが受けなかったね。」
「いつかドーバー海峡を泳いで渡りますみたいに言うね。あんな試験は碌でもない。」
「ボクはそうは思わない。ビブンセキブンの問題だって出るしね。パパはその前で腹が痛くなって辞めただろ、算数。ママが言ってたよ。ビブンセキブン面白いのに勿体ないってね。」
「ところで、今どこに住んでいる?」と僕は痛くなりそうな腹を押さえながら尋ねた。
「それって本気で聞いてる?」と長男は言った。
「本気の訳がないだろ。それではまずはその理由を教えてやろう。」と言い淀んだところで「スーパースターだからだろ?」と小学校6年生の長男が先じた。
「いい加減にそのキャラをやめてくれって言ってるんだ。」
「キャラではないさ。そして言葉の綾でもない。」
「いくら何でも裁判にマントをつけてくのはやり過ぎだと思うよ。すまないが、パパとは話してはならないとママの弁護士が言っている。」
「お父さんも弁護士だ。」
「パパよりもっと偉くて優れた弁護士だよ。蕾っていうね。パパよりずっと偉くて優れた先生がパパと話しちゃダメだって言っている。だったら話しちゃダメに決まってるじゃないか。」
「そんなの戯言だ。」
「では、信じてはいけない理由があるかい?あっそういえば、パパ蕾先生の受任通知を受け取ったのにママに電話したらしいね。」
「なんでそんなこと知っている?」
「蕾先生がママと話していた。それ法律で禁止されている直接交渉っていうらしいね。弁護士がゼッタイにやってはいけない。蕾先生がママの代理でパパのことを弁護士会に訴えるらしいよ。チョウカイ何たらって請求だ。あんまりにもパパが惨めだから言っちゃったよ。つい口を突いて出たんだから悪意はないよ。事実だしね。これって真実?まぁどっちだっていいや。ついつい言っちゃったのは事実の方だね。」
「お父さんはお父さんとしてママに電話したんだ。それの何処が悪い。」
「何処が悪い?ブーだ。それは事実じゃなくて評価さ。評価じゃなくて事実を訊ねないと。ところでさっき、パパ自分のことを弁護士だって言ってなかった?」
いくら預けるところがなかったとは言え、こいつを法廷技術研修に連れて行ったのを後悔した。長男は期別年齢に関係なく受講生の弁護士を「この子」と呼ぶ有名な宗教団体の教祖に似たキ印の刑事弁護専門弁護士に「ブー。それも評価だね」と諭されている僕にそうしたようにヒッヒッと笑いながら再び雲梯を登り始めた。小さい頃、早朝のテレビ番組で観た椰子の木を登るモンチッチさながら小気味よく雲梯を登っては降りた。しばらく奇妙な上下運動を繰り返えす内、長男は神からいかづちを喰らったかのように激しく目を瞑りながら蠕動した。
「控えめに言ってパパはとんまだね。お菓子で言えば、何だろ。バナナスプリットみたいだ。ところで、あの動物は何て名前だっけ?ジュゴン…。あぁマナティだ。」
僕はぐったりと動かなくなった長男にもっともっと幼かった頃の天使の幻影を見て、賽銭箱代わりの半ズボンへ千円札を捩じ込み、その場を後にした。
マンションに帰るとチャイムが鳴った。エントランスのモニターを見ると赤い線の入ったヘルメットを被った郵便局の配達員が立っている。汗みどろの配達員の胸には茄子紺色の封筒があった。その色の封筒が示すのは一つしかない。特別配達と記された弁護士会からの封筒を開けると案の定、綱紀委員会の審査開始通知書と妻名義の懲戒請求書が入っていた。内容は予想通り僕が妻に電話したことが弁護士として「品位を失うべき非行」に当たると言うものだったが、驚くことに請求者手続き代理人は海老寺蕾である上、綱紀委員会の委員長のところにも海老寺蕾の名前があった。ゆっくりと瞬きをして確かめたが、そんなことをしてみても海老寺蕾という名前は変わることがない。同姓同名の弁護士がいたのだろうかと思ったが、そんな訳もない。
気を取り直して新聞を読んだ。記事の内容はまるで頭に入って来なかったが、暫く読み進めると衝撃のスクープが目に飛び込んで来た。地方版の事件欄に連続放火殺人犯の記事に連なって「樽井正義弁護士(38歳)離婚紛争の最中に妻に直接交渉した疑い。所属弁護士会が事案の審査を開始。」と顔写真付きで報道されている。これで懲戒請求が通るも通らないも僕は世の中から事実上の懲戒を受けることとなった。ただ、幸か不幸か僕は他の弁護士のような順応主義者ではない。足繁く弁護士会に足を運んで、愚にも付かない会長選挙や憲法を考えるミュージカルの練習に参加したことは一度もない。彼らは会派を組み、万が一懲戒請求が来たとしても会派の領袖に揉み消して貰おうと息を吸って吐くように胡麻を擦り、もはや目に見えないほど高速で尻尾を振り続けている。そして、僕が強制的に所属させられている弁護士会に会派はなく、4K深紅の共産党単独政権だ。この弁護士会があるお陰で僕は純粋な弁護士として存在することはない。自分自身の品位が赤い奴等によって勝手に決められてしまうからだ。しかし、それで構わない。何があったとしても僕があの順応主義者の群に加わることはない。僕はスーパースターだ。たとえ本当に懲戒処分を食らっても気を取り直してマントを新調しに行くだろう。