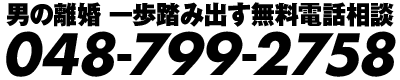離婚は弁護士によって着々と進められていった。離婚に向けての決定事項は、親権は智恵子に。慰謝料はなし。養育費は娘2人が大学を卒業するまで。面会はお盆休みとお正月の2回と達正の仕事都合上、不定期に年10回まで。達正の両親から購入してもらった車は達正に。離婚の条件が全て決まり、あとはこどもたちに説明するだけとなった。
夢にまで見た「離婚」が成立するためには百合と梨花の気持ちに寄り添っていかなければならない。智恵子にとっては生きる希望である「離婚」はこどもにとって希望ではないのだ。こどもたちは長女の百合が中学2年生、次女の梨花が小学校5年生になっていた。智恵子はとにかくこども達と納得した上で離婚したいと強く思っていた。
智恵子が百合と梨花に離婚を切り出すと長女の百合は、
「お母さんのことはよく見ていたから、大丈夫だよ。」サラッとそう言った。百合は母親の智恵子が達正に散々振り回されているのを見ていた。百合自身も家が貧しいという理由で我慢することが沢山あったし、達正が時々家に引きこもる様子を疎ましく思っていた。夜中に聞こえる夫婦の声が穏やかな話し声ではないこともちゃんとわかっていた。
「寂しくないの?」
「だってほとんどいなかったし、いたとしても部屋から出てこないし…」
「ごめんね。」
「お母さんが謝る事じゃないよ。私がいるから、お母さん1人じゃないよ。もう十分わかっていたし、いつかな〜?くらいに思っていたよ。」
智恵子は涙が止まらなかった。やりきれない気持ちをぶつけてしまうのはいつも百合だった。そんな百合はいつも智恵子に気を遣うのではなく真っ直ぐに向き合ってくれた。時には反抗し、時には智恵子の肩を抱き慰めてくれる時もあった。
次女の梨花は責めるでもなく、怒るでもなく、ただただ目に涙をいっぱい溜めてじっと智恵子を見つめた。言葉にならない思いは父親への思いそのものだった。どうして他の家族のようなお父さんではなかったのだろう。どうして私にとっては優しいお父さんなのに、どうして…。
梨花の無言の抵抗に智恵子も困惑した。こどもというのは生きることにおいて無力だ。親の手の中に自分の人生が握られている。
「そうだよね。寂しいよね。梨花のお父さんだもんね。」
「うん。」
「お父さん優しかったよね。遊びに連れていってくれたし、旅行とかも行ったよね。」
「うん。」
「梨花にとってのお父さんは変わらないよ。ずっと梨花のお父さんだよ。」
「うん。」
「でもごめん。お母さんはお父さんともう一緒にはいられないの。」
「…」
数日間梨花は無言だった。まだ無邪気な小学5年生の梨花にとってお父さんがいなくなるということの重さを、智恵子は解っているようで解っていなかったのだ。ただ離婚したい一心で進んできたけれど、百合と梨花にとってのたった1人のお父さん。運動会でビデオ撮影してくれたお父さん、応援の声がビデオに入ってめちゃくちゃうるさくて、2人とも笑ってたな。みんなでスキーに行ったら、お父さん1人ですごい転んで笑われて、それなのに娘の前ではカッコつけてたな…。智恵子の頭に達正のお父さんとしての顔が次々と浮かんだ。達正はこどもたちにはずっと優しかった。あまり家に帰っては来なかったものの、帰ったきた時には止まらない2人のおしゃべりに耳を傾け、2人を抱きしめた。
数日後、智恵子と百合と梨花は山を登った、「離婚」することを目標にして、登る度に前よりも少しでも高い山を登ってきた。離婚しても1人で立派に子育てできるように、最初から計画を立ててちゃんと登り切って下山出来たら、私は絶対に離婚しても2人を幸せにすることが出来る。自分に課した課題でもあった。梨花は登っている時ずっと無言だったが山頂に着いた時、ポロポロ涙を流しながら「離婚わかった」と呟いた。智恵子も百合も泣いた。山頂の晴れて澄み切った景色と涙が混ざり合う、鳥が変な声で鳴き出すと百合と梨花は急に笑い出した。智恵子もつられて笑い出した、笑いながらも涙は止まらなかった。
「こんなお母さんだけど一緒にいてくれてありがとう。こんなお母さんだから解ったことがあるんだけど聞いてくれる?
2人ともこの先間違えてしまうこともあると思う。間違えたらおしまいにしないで、自分が幸せに思う道を諦めないで見つけてほしい。間違えたら引き返せばいい。違っていると思ったら何回だってやり直せる。自分たちが選んだ道で精一杯頑張って。お母さんは離婚を選んだけど、家族みんな幸せになるようがんばるね。」 登山は沈黙だったけれど、下山はみんな吹っ切れたように笑っていた。
達正は家を出ていった。こども達には何も言わずに。こどもの前では相変わらずカッコつけたかったのかもしれない。カッコつける言葉が用意できなかったから無言で出て行ったのかもしれない。それとも情けない姿をこれ以上見せるのは嫌だったから黙って出て行ったのだろうか。結局達正の本音は聞けなかった。だけどいつだってすぐ自分の都合で出ていける達正が、智恵子はいつも羨ましかった。智恵子はどんなにこの家から逃げたくても、逃げられなかった。幼いこどもたちを置いて、出て行くことなんて出来なかった。智恵子はボソッと呟いた。「出ていけていいよね。私はどんな時だって、2人の娘を育てるためにこの家から離れられなかったのに。」
離婚してしばらくはぼんやりした日々が続いた。大きなエネルギーを使い果たした脱力感と、もう毎月達正の補填にビクビクしなくてもいい大きな安心感と、憎悪に変わってしまった達正の存在からの開放感は、智恵子にとって幸福そのものだった。