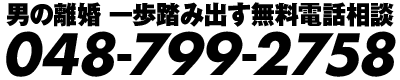男としての尊厳を全否定されたような感覚と、後悔のようなやり場のない感情に押しつぶされそうになりながら彰はそれから3年ほど悩みに悩んだ。何度となく一人で涙を流しとにかく悩み尽くした。里奈に対する嫉妬というのは一瞬湧き出てこなかった訳でもないが、それよりもこの先背負っていく負の感情の重さを考えた時の絶望の方が強かった。一通り精神的な苦悩を味わった後、彰は自分の人生の再建に取り組むことに決めた。里奈との対面では話にならないのは分かりきっていたため、早々に弁護士に相談することにした。
職場の先輩の友人だという沼田弁護士を紹介してもらった彰は、法律事務所に足を運んだ。
「よくわかりました。彰さんのケースは決して珍しいことではありません」男性側の離婚の代理人を専門とする沼田弁護士は言った。
「そうなんですか。この場合どうなってしまうのでしょうか」
「まずは、ここに至るまでに散々苦しんだ彰さんに幸せになっていただくのが一番重要です。そのために私がお役に立てれば光栄です」
「まず仁さんの親権ですが、特別なご希望がなければ放棄するのが得策です」沼田弁護士は言った。
「最愛の息子が子供じゃなくなるというのは正直複雑な思いです」彰は言ったが、沼田には確信があるようだった。
「もちろん彰さんにとって仁さんは愛する息子さんのままです。ただ、それは人と人というこれまで以上に本質的な付き合いとなります」
「まず離婚によって、彰さんには法的に里奈さんと仁さんの扶養義務がなくなります。まずは生物学的な父子関係にないことから親子関係不存在の訴えを起こします。これを結婚を継続できない十分な理由として、並行して離婚の訴えを起こすことで対応していくのがよろしいかと思います」
「里奈に仁を養う力があるように思えませんが」
「相手方の親御さんは」
「健在です」
「年齢や経済力は」
「問題ないかと」
「仁さんは相手方の親御さんの養子に入るのが理想でしょう。相手方に養育能力がないのはもはや彰さんには関係がなくなりますが、誘導できるよう意見を準備していきましょう」
「相手方に慰謝料を求めたい気持ちはありますか」
「ありませんが、できれば仁との関係に時間を使いたいです。気持ちの整理がつかないのです。仁は私にとってずっと血縁のある息子でしたから」
「よくわかります。最初にも言いましたが、珍しいケースではないのです。このようなケースで、その後すべての精神的問題を解決してそれまで以上に幸せな生活を送っていらっしゃるお父さんとお子さんは大勢いらっしゃいます。今はご不安でしょうが、ご心配いりません」
「先生にお任せします」
「それから仁さんも彰さんと同じ苦しみを抱えているはずです。寄り添ってあげていただけると、必ず仁さんだけでなく彰さんの力になりますよ」
「仁さんと彰さんはいわば被害者です。それでもこの苦しみから必ず這い上がれるはずです。苦しい日々はもう終わったと私が断言しますので、とにかく前向きに考えてください」
「よろしくお願いします」
彰は全ての手続きを沼田弁護士に一任した。
翌週には彰は他のアパートを借り、別居を始めた。徐々に本来の自分を取り戻して行く感覚を味わう彰であったが、一方で仁のことも気がかりではあった。不思議なことに、それまで自分の一部のように感じていた仁との距離が急速に遠のいていくのがわかった。それだけでも別居の時間というのは残酷であり、またそれ以上に意義のある期間でもあった。この先、彰は仁と血縁を超えた一人の人間として向き合っていかなければならないのだ。
彰と里奈は3回ばかりの調停を経て、正式に離婚した。いくつかの要求の食い違いを驚くほどスムーズに捌いていく沼田弁護士を前に、彰はまるで親の手に引かれるままに歩く子供のようであった。もっとも里奈は最後までDNA鑑定の結果を認めなかったようだが。
来来軒に彰と仁がいるのは、それから3年後というわけだ。この3年間、二人は月1回くらいの頻度で会い、お互いの心を埋めるような作業をしてきたのだ。これは13年間も親子の絆を育んできた二人にとって互いに必要な時間であった。
「俺が親父の本当の子供じゃないって言われてから3年くらいたったかな」仁が言った。
「そのくらい経つか。俺は結果が分かった時、相当なショックで頭が真っ白だった。その結果を受け入れるまでに3年はかかったよ。お前に話したのが中3の時だったよな。多感な時期だったからお前に話すか、俺も母さんも悩みに悩んだし、一生話さないで置くという選択肢も実は俺にはあった」
「俺の方は正直今でもキツイよ。父親が誰かわからないなんてさ。そんなやつ周りに一人もいないんだから。今さらだけど、結婚を続けることはできなかったの?」
「難しかっただろうな。ほら家の中めちゃくちゃだっただろ。夫婦喧嘩ばかりでさ」
「確かに」
「それより、お前の母さんがDNA鑑定の結果を受け入れなかったのが俺にとっては辛かった。信じ通せば真実になるとでも思っていたみたいだった」
「母さんも絶対自分の意見、曲げない人だもんね」
「俺は事実を受け入れて前に進むべきだと思ったのは、その方が3人にとって良いと思ったからなんだ。だからお前に話した後、もう一度別の鑑定会社で鑑定しただろ。それでも母さんは受け入れようとしなかったよな。それ以降は話は平行線だった。そこに折り合いを付けるのは難しいよ、それぞれの考えだからさ」
「俺は本当の父親が誰か分からないって宙に浮いちゃった感じ。と言ってもどうすることもできないんだけどさ」
「血が繋がっていないことがわかったけど、お前との思い出は山ほどあった。俺は親としてお前に何度も救われた。その思い出は色々あってもまったく消えなかった」
「俺には親父と母さんのいる家族が全てだったからね」
「血が繋がっていないと分かっても、家族の思い出はたくさん残ってる」
「俺も親父が優しかった記憶しかない」
「いずれにしても、今もこうして話をしている。こんなのも珍しいよな」
「親父、友達少なそうだもんね」
「ま、それはそうかもな」
一つ二つの短い会話を交わした後、彰は「そろそろ行くか」と言って立ち上がった。
「今日は俺が出すよ。昨日バイト代入ったんだ」と仁が言った。
「バイト続けてるのか。それはいいな。支払いはさっき俺が済ませといた。ビールも飲んだし。気持ちだけもらっとくよ」
来来軒を出た時には、時計は午後2時を回っていた。
仁は新宿まで移動しバイトがあるのだという。肩を並べて駅まで数分歩くのも恒例だ。
「ほんと、俺の周りバカばっかし。親父はまともなほう。俺ばあちゃんが死んじゃったらこの先どうやって生きていくんだろう」
「ばあちゃんは元気だからまだまだ大丈夫だよ。そういえば、お前誕生日来月じゃなかったっけ」
「そう。17歳」
「うまいパスタ屋を見つけたんだ。今度行ってみるか」
「マジで?行きたい」
「俺は、こうやって時々お前と過ごす日曜は結構好きなんだ」
「ああそう。ま、俺も楽しいよ。やっぱ親父に聞きたいこととかもあるし。大人の男の人って話す機会ないからさ。学校の先生はキモいやつしかいないし」
「でもさお前に彼女ができて、日曜は彼女との時間に使おうっていうんなら、こんな時間は無くなってしまうだろうな」
「今のところ平気。俺今バイト人間だから。ちょっとやりたいことがあって金を貯めたいんだ」
「そうか。やりたいことがあるっていいよな。頑張ってるお前を見てると俺も頑張ろうという気持ちになるよ。俺は応援してるよ」
「親父ありがとう。今日は本当に。また」
駅の改札前で彰と仁は別れた。
夏の終わりの爽やかな風が、改札前のコンコースを心地良く吹き抜けていった。