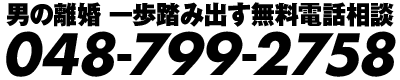ふと、わたしの人生にとっての一番の美味しい飲み物は何だったのだろうと考えた。幼少の頃、シュガーコークはご馳走で、誕生日にしか飲めないものであった。それはレトロな瓶だけが弾倉のように詰められている販売機でコインを入れても自動的に何かが音を立てて出て来ることはなく、ギザギザの蓋から感じる痛みが喉の渇きに優ってしまうもので、幼いわたしはいつも母親に引き抜いて貰っていた。そのシュガーコークも今や瓶から缶に、ペットボトルにもなり、2リットルの巨大なのもあって水よりも廉価な飲み物になってしまった。もはや手に入らないのではないかと不安になってしまう不二家のネクターはお菓子で言えばマールボーロのようなもので、おそらく正味の桃果汁は殆どと言っていいほど入っていない。それなのにどうして桃の味がするのか子供心に不思議だったが、今飲むともしかして飲めたものではないのではないかと思ってしまう。そう思う理由は子供が食べていたマールボーロを食べて幻滅した鮮明な記憶が残っているからだった。青年になり美味しい珈琲を探し歩いたことがある。ドリップを研究し、サイフォンを揃えようかと思い始めたときに渋谷にある水出し珈琲店に辿り着き、足繁く通った。煮え滾った悪魔の血を思わせる濃さの珈琲はダッチ珈琲と言って、細いビーカーが遊園地のジェットコースターのように畝り狂っている薄暗い店内は何かの研究所のようでもあった。久しぶりにその珈琲を飲もうと思って渋谷に行ったが、かつての狂騒とは裏腹にパルコすら無くなった渋谷はわたしにとって天然の幽霊都市で悍ましい恐怖を感じさせる街だ。中学生に作らせたインスタントコーヒーより濃いスターバックスのドリップ珈琲はシュガードーナツと奇妙にマッチし、エナジードリンクでも感ずることのできない温度の鼻息が放たれる。それを楽しむマスクを外した人間たちの様相は、現代の阿片窟を呈する。ダッチ珈琲の二重の意味での命日がいつの日だったか知る由もないが、もう長くスターバックスに通っておらず、裁判所の駐車場が満車で国道沿いのスターバックスの駐車場に止めざるを得なかった時でも割引きのコインを貰うことなく、わたしは鴇色に表示される金額を純粋に支払う。わたしの珈琲遍歴に話を戻すが、友人宅に遊びに行って出して貰った珈琲の味に感動し「これどうやって作ったの?」と訊いたら、その友人が「ネスカフェだ。ゴールドブレンドだけどな。」と言って呆気なく終末を迎えた。そういえば昨年の秋、大井町のゴールドジムでゴリ高梨に「減量時にはバナナは辞めて下さい。」と言われ「分かりました。」と実直に約束した直後にその一階でゴリ高梨の幻影に怯えながら飲んだバナナシェイクは格別に美味しかった。ただ、それは自分をゴリラに模した男にバナナを柔らかく禁じられた禁忌破りのエクスタシーのようなものであり、砂漠を生き長らえた男がオアシスで飲む水のようなもので、わたしはわたしの大事なクライアントに割くべき時間を削ってまでそう言った意味での美味しさを語りたい訳ではない。横浜で裁判があった時は必ず中華街に立ち寄り、中国人たちに顔を覚えられていた時期があった。ある店に入り、紹興酒を注文した際、窓がない部屋に迷い込んできた秋茜のような不思議な残影に囚われた。それはと或る飯店の出店の看板に載せられた「氷点下ハイボール」という表示の残影であった。わたしは同席者たちに一本電話を掛けてくると嘘を言って、その幻影を蛾のように辿った。出店に立ちその一杯を注文して飲んでみるとそれは永久氷土の雪解け水を利用して作られたのではないかと訝るほど冷たく、興醒めと酩酊への恐怖をスレスレで片肺飛行するかのようなウヰスキーの濃度であった。わたしは会合を終えると足早にその出店でもう一杯を注文した。中国人の青年は「すみません。さっき機械の電源を落としてしまいました。」と言った。どうやらその飲み物は機械によって作られているようだ。次の機会にその店に行くと、今度は中国人の女がそこに立っていた。一杯目を注文して一息で飲み干すと、かつて見たのと同じ幸福な薔薇色の雲が周りに現れた。「これはどうやって作っているのですか?」と禁断の質問を投げかけた後、すぐに愚問だと嘆くことになる質問に20代後半の若い中国人はわたしの日本語をよく聞き取れなかったそうで、「これはとても高級なお酒を利用してあたしが作ってます。」と小鼻を大陸系に膨らませた。わたしは彼女に気がつかれないように、煌々と照らされた看板を盗み見するとそこには悪びれもせず「ブラックニッカクリア」と書かれてあった。「ブラックニッカクリア」は高級とは言えないブレンデッドウヰスキーのブラックニッカのエントリーモデル即ち最下級のウヰスキーで、北海道のセブンイレブンで説明するとザンギに合うと北海道民にこよなく愛されているサッポロソフトの少し上の部類に入る。びっくりしたフリをして二杯目を注文し、わたしの躰の周りに訪れる幸福な薔薇色の雲を再び見つめ直した。一体全体どうやって作っているんだと酔いに任せて店の中を覗き込もうとしてそれを中座する時間帯が暫く続いたが、結局、今に至るまでそれをしていない。なぜなら、それは竜宮城で働く乙姫たちのシフト表を盗み見するようなもので何一つ生産性がない。言ってしまえば野暮であるからだった。そのようにして出会った美味しい飲み物である「氷点下ハイボール」も最後に飲んだのはいつだったか忘れてしまった。結局、わたしの人生において一番美味しい飲み物は何だったのか、わたしには分からない。ひょっとするとこれからもずっと分かることがないような気がしている。