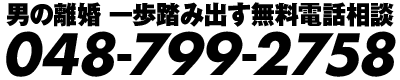人間の最も根源的な感情である恐怖を感じることが、鮮明でいつまでも色褪せない記憶となることは、誰も否定出来ないだろう。その恐怖の対象が人間ではなく、何かの生物であればそれはもっと鮮明なイメイジとして残ることに違いない。
このゴールデンウィークにふとしたきっかけで広島に帰ることになった。帰ると言っても私の実家は神奈川にあり、あまり好きな場所ではないが、厚木という場所に未だ存在している。広島には呉に母方の家があった。私はどちらかといえば、厚木よりも断然、呉の方が好きだ。呉には沢山のいい思い出あるが、その一つで母が生まれ育った海で魚を釣ったというのがある。
当時、私はちょうど小学6年生で夏休みは終業式から始業式の前日まで広島にいた。夕方塾から帰ると、やおら祖父に小銭を貰っては、その頃から腰が曲がり切った主人が営む釣具屋にゴカイを買いに行き、引き返しては山あいを背にした防波堤から独り魚を釣っていた。釣れる魚といえば、櫨が多かったが時にはカレイやアイナメが釣れた。櫨よりもカサゴが多かったかも知れない。カサゴが釣れると針を飲むので、仕掛けがダメになってしまう。防波堤には足で踏んで針を引き出そうとしたが、それが出来ずに踏み潰されたカサゴが干物のように散乱していた。
あともう少しで厚木に帰らなければならないという日、その日は昼過ぎから投げていたが日暮れに際しても一匹も釣れなかった。そして、夜のしじまが訪れた。釣竿を投げる防波堤の切れ目に街灯はなく、わざわざ少し離れた県営アパートの灯りを借りてゴカイを付けていたのだが、そんなゴカイも数える程になったその時、私の竿に嘗てないほどのアタリが起きた。糸の先で悶絶する魚の躍動を直に感じながら、私の心は今釣り上げられようとしている魚と同じように躍動したが、暫くするとその躍動に少なからぬ恐怖の色が帯びるようになった。そして、月明りに微かに照らされた得体の知れない魚が海面に現れ始めると私はウツボでも釣ってしまった、どうやって針を外して海に捨てようかと考えるようになった。その魚は今まで釣り上げた魚とは比べものにならないモノであることは確かなことだった。私は釣り上げた魚が尾鰭を懸命にアスファルトに叩きつける音を聴きながら、県営アパートの街灯の下に針をつけたまま持って行き、恐る恐る近づいて目を凝らした。私の釣り上げた魚はおどろおどろしいウツボなどではなく、薄暗い街灯に重ねた砂埃の上からも分かるほど綺麗な鴇色をした鯛だった。私は、街灯の下でピタピタと跳ねていた砂埃に塗れた鯛を今でも覚えている。幼少期の数少ない良い思い出である。
このゴールデンウィークに私が母親の居る広島に帰ったのは他でもない、妻が育休明けで病院に復帰したため、幼少の次男を看るものが居なくなったからである。祖父が死んで疎遠になった広島はつい最近まで高裁に事件が係属していたが、私は裁判が終わるとお好み焼きすら食べずにすぐに東京に戻った。かつての軍港都市である呉は私にとって、歴史上の都市を超え、地図上の都市に移り変わろうとしていた。
広島から呉線に乗り、かつて多くの戦艦を戦地に送り出した軍港都市のイメイジが色褪せない呉の風景を右手に見ながら母の家に着くと、私は子供からせがまれるより前にゴカイを買いに桟橋までの山道を蜻蛉返りした。腰の曲がっていた老人の店が廃業していたのは敢えて確認するまでもない。桟橋の大きな釣り具屋で投げ釣りセットとともにゴカイを購入し、その足で原体験を彩るあの防波堤に向かった。
子供に親である私の原体験を追って体験させようと勢い勇んで海に仕掛けを放ったものの、海はいつまでも静寂を貫いた。そしてあの日と同じように夜のしじまが訪れた。子供が「この海サカナ居ないね。」と言い始め、32年の時の流れを魚が釣れないという事実を持って知る他ないように思い始め、私自身、生じる可能性の乏しい原体験の再来よりゴカイのついでに桟橋のスーパーで買った32年前に私が釣り上げた鯛さながらに時めく鴇色のカープ酎ハイに心が傾き始めていた。
そして、私は防波堤に立て掛けていた釣竿を徐に取り上げ、やれやれとリールを巻き始めたところ、驚くことに幾ばくの手応えがある。ただ、それは心躍らせるようなものではない。藻でも引っ掛かったのだろうと巻き続けると、どうやら藻ではないのだと思った次の瞬間、たゆたう海面から人魂のようなものが現れた。不気味な違和感が私たちに伝染した。その違和感が確実なものとなったのは、何やら奇怪な生物を釣り上げたということが判明した後のことであった。それは、鯛でもカサゴでもない、およそ20センチ近くの軟体生物であった。不気味な感覚は見るもの全てに伝染しただろうし、御多分に漏れず私たちに叫び声を上げさせた。「地球外生命体が釣れた。政府に報告しよう!」と子供が叫び、私は真剣に思いつくまま官庁の連絡先を頭の中で選択した。結局後で分かったことだが、その軟体生物は赤ナマコだった。ただ、その時アイフォンの光に照らされた軟体生物は子供が言うように既に不惑を過ぎている私の目からしても地球外生命体にしか見えなかったのだ。「動いているよ、今動いた!」と子供が叫んだが私が竿を持っていたためそう見えているのは分かっていた。ただ私自身左臀部に不気味な生暖かさを感じ、眼前の地球外生命体が人智の及ばぬ能力で私の左臀部に乗り移ってきたんだと思い、ギャッと叫びをあげたが、その生暖かさは子供が寒いと言ったことで母の家から持ってきた携帯用カイロの温もりであった。私は、子供の前で威厳を喪わせた赤ナマコに怒りを抱いた訳ではなかったが、父としての最低限の名誉を確保するため、その奇怪な生物を仕掛けごと海に蹴落とした。赤ナマコは釣り上げられたときと同じく人魂のように漆黒の海にゆっくりと沈んで行った。
その3日後、私は他の子供と一緒に沖縄県の宮古島にいた。名目は、来年の中学受験のための勉強合宿ということだったが、モンスーンのような大雨の中で私は琉球泡盛に酔い潰れ、深夜目を覚ますと、子供はリゾートホテルのwi-fiを利用し、目を爛々に輝かせてiPadのゲームに興じていた。翌日、取り繕うように勉強を見た夕方、折角だから海に出ようという話になった。
まだ5月とはいえそこは南国の島、海に入っている人は少なくはなかった。皆、シュノーケルで何かを探していたが、何を探しているのかは予備知識も興味すらなく、ただただ恐妻或いは恐母から逃れてこの島に辿り着いた私たちには知る由もなかった。子供が海に入り小魚を追いかけている間、私は浜辺でカールゴッチ式プッシュアップを延々と繰り返した。浜辺でプッシュアップを続ける中、身体を外らせる度に少し離れた沖の大きな岩が飛び込んで来て、徐々に私の意識を占領し始めた。その岩は浜からどの程離れているかは目視では分からなかったが、恐らく私の背丈からして足が付かない位置にあるのは明らかであった。ただ私は岩まで泳ぐという囚われた願望から逃れられないことを早期に悟り、海に入った。そして、小魚を追う長男に向って「今からあの岩まで泳ぐから見ておけ。」と朴訥に伝えた。
取り敢えずは足の届く場所まで行こうと海の中を歩くと、火山の噴火で出来た島ならではゴツゴツした岩が私の平常心を苦めた。海面が顎に達し、そろそろ泳ぎ始めようとしたところ、ふと後ろを見ると子供が私の腕にしがみ付いている。私があの岩まで泳いでもそれを見届ける人間が溺れ死んでは元も子もない。そう思った私は慌てて引き返し、そのくだりを3回ほど繰り返したのち、私は「動くな。そこから見ていろ!」と子供を激しく牽制した。そして、子供がまだ胸元辺りの位置で止まっているのを確認しながら自らの下唇に海面が届くか届かないかのところまで進み、私は初めてその岩に向かって泳ぎ始めた。浜辺から見る波と実際に沖に出て見る波は全く違っており、浜辺から見る漣は沖で泳ぐとまるで時化のそれにも思えた。既に午後5時を回っており、シュノーケルで何かを探していた観光客もハケてしまい、眼前には私と岩以外ただただ沖の方に向かって海が広がるだけだった。
そうは言っても、軍艦を魚雷で駆逐されて死ぬことを一時猶予された水兵のそれとは違うリゾート地での思いつきの遠泳である。本の先にある岩まで泳いで、岸まで帰るだけだ。そう思いなす私の眼前に突然、思いもよらぬ生物が現れた。それはあまりにも思いもよらぬ生物であり、成人後の自衛隊で初めて泳ぎを覚えた私の正気を奪うのに十分だった。水族館やニュース映画でしか見たことのないウミガメが悠然と私の前に姿を現したのである。岩まで泳ぎ、後は浜に戻って父親として見せ付けた尊厳を奏で直すだけだと思っていた私が思いがけず遭遇した生物に私は完全に我を失った。そして突如、私は自身が溺れるか、ウミガメが死ぬかの二者択一の構図に襲われて後者を選択し、渾身の力でエルボーをウミガメに叩き付けたのである。
渾身のエルボーは当たったか分からず、ウミガメが静かに海の中に消え行くのだけを私は眺めた。その後、私は更に冷静さを喪い、ウミガメがいるなら他の生物、例えば鮫や蛇、もっと言えば鯨、いや、謎の生命体すらいるやに違いないと思い、虎河豚のように不器用な旋回を見せた後、全速力で岸に向かってクロールを始めた。あまりにも全力でしかも殆ど息継ぎなしで泳いだため、砂浜が腹に当たるその直前まで自分が果たしてどこにいるかも分からなかった。そして、虫の息で砂浜まで辿り着くと、私の身体の四肢それぞれに生命が宿ったように脈打ち、痙攣するのが見えた。痙攣に任せ、ゲラゲラ笑いながらやって来た子供と飽きるまで半ば半狂乱になって、しまいには涙まで流してゲラゲラと笑い続けた。
あれから1ヶ月ほど時が流れたが、私は自身が放った2発の一撃を折に触れて思い出す。赤ナマコには間違いないが、あのウミガメにも私の放った一撃は当たったに違いないと私は信じている。赤ナマコが海の底でまだ生きているかどうか知る由もないが、あのウミガメにとって私のエルボーは何の痛手にもなりはしまいだろう。しかし、それでも尚、何かの折、彼の体の奥であの一撃は微かな疼きを誘うに違いないと私は想像する。それだけがせめてもの彼らと異なった生物である私からの彼らへのメッセイジなのだ。
独り雑事に疲れた深夜の事務所で、東京のバーでいたずらにマティーニを啜って帰る明け方の道の上で、或いは飽き飽きするほど冗長な判決言渡しの合間に、私はふとあの時出会った赤ナマコのことを思い、独りきりだったウミガメのことを思い出す。思い出すだけではなく、あの赤ナマコに、あのウミガメになりたいと無性に思うことがある。そして、その想像は私を蘇らせる。あの奇怪な生物になった私を、彼らになぞらえて思うことで、私はなぜか私を私自身として感じることが出来るのだ。一点、誰かが放った一撃に負うた小さく深い痛みを交えながら。その痛みを抱きながら、瀬戸内の漆黒の岩底で佇む私を、またあるいは、吹きすさぶ南風の中で滾った原始の海に落ちる紫の雷の閃光の中を激しい雨にうたれながら狙った獲物に向かって忍びよっていく私を、彼らになぞらえて思うことで、なぜか私自身として感じることが出来るのだ。